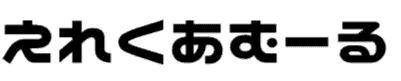この記事はで読むことができます。
だんだんと気温が高くなっていき、夏祭りの時期になってきました。
夏祭りに困ることは、浴衣の着方かもしれません。
どうしても蚊が多くなるときがあるので、浴衣を着る場合には、気をつけないといけませんね。
夏祭りでは、おみこしが出るところもあります。
ただおみこしを出したいからというわけではなく、おみこしを出す理由があります。
夏祭りの浴衣の着方・おみこしを出す理由など、夏祭りにかかわる説明をしますね。
夏祭りはどうして行うのだろう?
全ての夏祭りに共通しているのは、夏の暑さに負けないという意味かもしれないです。
昔から続く夏祭りには、お米の豊作や暑い夏に体を壊さないようにという意味があります。
暑い日が続けば体がついていかなくなってしまい、夏バテもあるでしょう。
夏に負けないために、暑くても健康に、そして秋の稲刈りのときにお米がたくさんとれるようになってほしいという願いがほとんどです。
夏祭りは神社で行われることが多いですが、神社で神様にお願いをするというのが本来の意味です。
夏祭りにおみこしを出すところもありますが、大きいおみこしは、京都の祇園ですね。
京都の祇園のお祭りは、病になってしまう人が多く、病を治したいという意味で祭りがあります。
場所により夏祭りには意味はありますが、多くは豊作と体のトラブルにならないようにという神様へのお願いです。
夏祭りにおみこしを出すのはなぜ?
夏祭りで見かけるおみこしだと思いますが、なぜおみこしを出すのかを考えてみましょう。
おみこしは、漢字で書くと「御神輿」という難しい文字になってしまいます。
おみこしの「輿(こし)」というのは、人のせるという意味があります。
ということは、おみこしという漢字から考えると、神様をのせるという意味ですね?
おみこしは「ワッショイ」というかけ声など(笛もありますが)で持ち上げ、はっぴを着て足袋(たび)を履いた人たちが多く見かけると思います。
夏祭りでおみこしを出してかついだり、おみこしが近所を通ると、神様がお米の豊作や体のトラブルを治めてくれるといわれています。
おみこしのテッペンには飾りがあることが多く、飾りのところに神様が降りてくるといわれています。
夏祭りのおみこしをかつぐときに法被を着るのは?
夏祭りになるとおみこしをかついで、法被(はっぴ)を着た人たちをよく見かけると思います。
場所によっては、夏祭りに上半身裸というところもありますよね?
おみこしをかつぐときの法被というのは、羽織(はおり)の形が江戸時代に変わったとされています。
おみこしをかつぐには、さすがに着物では動きにくいということもあります。
そこで、江戸時代には着物の袖を短くし、半ズボンのような法被ができあがりました。
法被は夏祭りのおみこしをかつぐときだけではなく、時代劇にも出てきますが火消しの人たちにも愛用された運動着とも言えます。
当時は体操服やジャージのようなものがなかったため、着物をうまく加工し、夏祭りのおみこしをかつぐときなどに法被を着たとされています。
夏祭りに浴衣を着る由来はお風呂だった
夏祭りへ行くときに、浴衣を着ている人をよく見かけます。
浴衣というのは、平安時代のお風呂へ入るための麻でできた服が由来とされています。
平安時代には、「湯帷子(ゆかたびら)」といわれている、今でいう浴衣の由来となっています。
江戸時代になると、銭湯ができ始めたのもあり、お風呂あがりに着るための浴衣になったとされています。
「浴衣」という文字通り、「浴びる」と「衣装」の組み合わせのように感じますよね?
浴衣の由来から考えると、お風呂あがりに浴衣を着るのが正解なのではないか?と感じるかもしれませんが、気にする必要はありません。
さすがに何かの大事な用事に浴衣を着ることはないでしょうが、風通しがいいですし、夏の暑さに耐えられる夏祭りに着ていくことが悪いことではありません。
涼しげな感じがしますのでいいと思いますよ。
夏祭りの浴衣の着方とは?右左どっちが前?
夏祭りでは浴衣を着てお出かけしたいですよね?
温泉へ出かけたときに部屋で着る浴衣ではないため、ある程度の下着は男女共に着ておいた方がいいでしょう。
あまり短い浴衣は見た目にもよくないので、足首が見えるくらいの長めの浴衣を選んでおくのがいいです。
よく洋服を着るときに左前だとか右前だとか、言われていますが浴衣は和服として扱われていますので左が前になるように着ましょう。
右前の場合はお亡くなりになった方の着物ですので、注意が必要です。
浴衣の右前や左前に男性と女性の差はないので、心配しなくてもいいですよ。
夏祭りの浴衣ということもあり、蚊に刺されることもあります。昼間でも汗をかくことがありますので、足袋をはいておくと蚊に刺されるリスクは減らせると思います。
浴衣の帯は結び目が後ろに来るようにしてください。
浴衣を着るときの帯は前で結んでもいいですが、最後は後ろにすると見た目がよくなります。
夏祭りの浴衣の選び方とは?
夏祭りの浴衣の選び方というのは、どういう浴衣がいいのか気になるところかもしれません。
毎年トレンドがあるので、何がいいとは言いにくいですが、花の模様が入った浴衣が多いですよね?
無難な選び方で言えば、花の模様が入った浴衣がいいのかなと思います。
色は白や水色などの涼しげな色が毎年人気となっています。
その年によって変わることはあるものの、変わるとした場合には、柄(がら)が変わることがあります。
あんまり気にしすぎると、毎年のように浴衣を買わないといけませんので、涼しげな色がいいと言われています。
また、濃紺などの濃い色もありますが、夕方になると白の場合は、虫が寄ってくることもあります。
虫が寄り付かないように、濃い色というように夏祭りへ行く時間によってあらかじめ用意しておくといいでしょう。
まとめ
夏祭りの浴衣とおみこしについて説明してみましたが、いかがだったでしょうか?
夏祭りとは言っても、奥の深い地方の行事です。
夏祭りには豊作や体の調子が良くなるように、神様に来てもらうというのが本来の意味です。
今は屋台が出ており、縁日に近いものがありますが、それでも楽しめればいいのかなと思っています。
浴衣について、少し多めにふれてさせてもらいました。
浴衣の着方の説明もさせていただきましたが、必ず左が前に来るようにしてください。
法被を着ておみこしをかつぐのもいいですし、おみこしが来たときに「健康になれますように」とお願いしても良いでしょうね。
行く時間帯によりますが、暗くなった場合には注意するようにしてくださいね。
楽しく夏祭りを楽しんでください。